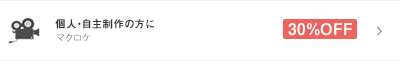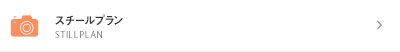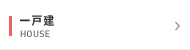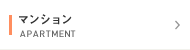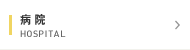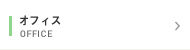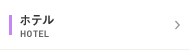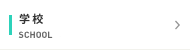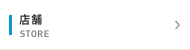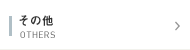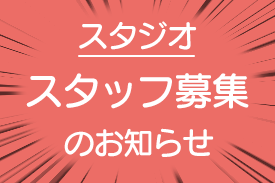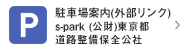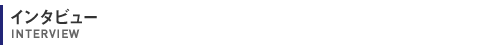第六回
ディレクター
齋藤朋彦さん
スタジオマン、という意味
 出会いといえば鍋島さん(弊社代表)のことも話さないとね(笑)。
出会いといえば鍋島さん(弊社代表)のことも話さないとね(笑)。
確か92年頃だったと思うんだけど、都内のオール・ロケでいろいろな物件をロケハンしてたんだけど、その中でまだオープンして間もない谷原病院スタジオに行ったときはじめてお会いしたんだ。
そこで印象的なエピソードがあって、監督は部屋が広すぎてちょっと気に入らない場所があったんだけど、鍋島さんが
「じゃあここに移動壁作るのどうですか?」
って率先して意見してくれたの(笑)。
なんだ横から急にって思ったけど確かにそこに自在に動く壁ができたら引きじりを調整できて便利なの。監督もそりゃいいねってことですぐに美術発注したんだ。
それだけじゃなくてその作品には女の子部屋のシーンもあったんだけど、当時谷原病院スタジオの上階に住んでいた一人暮らしの若い女の子に直接交渉してくれて、
みんなして「それは無理だろ~」なんて言ってたら
まさかの交渉成立、
その部屋で撮影できることになっちゃったの(笑)。本当にあの協力的な姿勢と積極的な行動力には驚かされた。
そこから都内のあらゆるロケ場所の相談に乗ってくれたりしたんだけど、いろんなアイデアを提案してくれるんだ、ほとんど実現しなかったけど(笑)。
でも実現できるできないは問題じゃなくて、そのアイデアの視線って完全にこっち側(作り手)の目線なんだよね。だから作り手に寄り添っているような感じがあって、それはつまりプラネアールの社風とも呼べるかもしれない。
それから永い付き合いになるけど、近年の山田洋次監督の作品には必ずプラネアールの現場スタッフが制作応援として就く流れが定着した。
木更津スタジオの映画『母べえ』を参考にした古民家が建ち並ぶロケセットが象徴的な例だけど、現場でいろいろ学んだ経験がハウススタジオ作りに活かされてると思う。ただ空き物件や居抜き物件を提供してるんじゃない、寄り添った経験を踏まえることで作り手を刺激するアイデアが詰まったハウススタジオを提供していると感じるんだ。
日本文化としての娯楽
 最近は撮影所専属の技術者というのが減っていきながら、たった一人でもカメラから録音から編集まで全部できるようなシステムになってきた。
最近は撮影所専属の技術者というのが減っていきながら、たった一人でもカメラから録音から編集まで全部できるようなシステムになってきた。
配信事業も増えてきてあらゆる映像コンテンツが存在している。つまりプロ・アマの垣根は低くなり、そういった環境下で平等に作品が制作でき外の世界に発信できる時代になった。
映画の在り方も変わってきて「配信作品を”映画”として扱うのか?」なんて議論が聞こえる時代にまでなったけど、その背景には劇場に足を運ぶお客さんが減ってしまう危機感があるんでしょう。
その気持ちはわかるし、やはり僕もフィルムに魅了された一人として劇場の大型スクリーンで多くの人と作品を共有してこそ映画だと思う。あの幸せな瞬間がたまらなく好きだし、みんなで語り合えるような家庭の中心にある娯楽でいてほしい。そう思えるのは、日本文化に映画が根付いている、と信じているからなんだ。
そういった意味で、松竹の看板であり伝統である『男はつらいよ』の新作が今年(2019年)公開されるのはとても意義深いものがあるよね。まさにみんなで笑って、みんなで感動して、みんなで楽しめる作品です。
どうせなら最近の『ボヘミアン・ラプソディ』みたいに応援上映なんかしてもいいね(笑)!これぞ日本映画っていう醍醐味をみんなで味わってほしいよ。